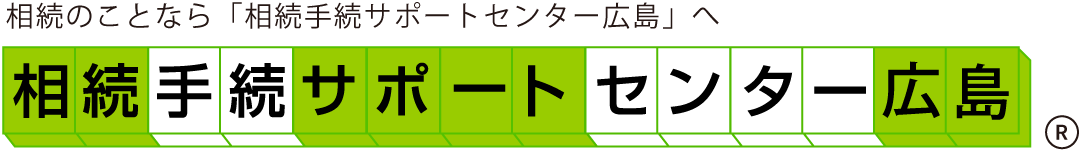家族が亡くなり葬儀が終わると、ゆっくりと故人との思い出にひたる間もなく、保険や年金、預貯金や不動産、
税金のことなどやるべき手続きがたくさんあります。
何をいつまでにすればいいのか、全体のおおまかな流れを把握してから手続きを進めていきましょう。
まずは遺言書の有無を確認しておきましょう。
5日もしくは14日以内
◆健康保険・厚生年金(会社員)・・・勤務先
後期高齢者医療制度、国民健康保険・・・故人が住んでいた市区町村役場で手続き
なるべく早めに
◆公共料金・固定電話・定期購読など
銀行口座が凍結されると引落しができなくなり、電気やガス、水道が止まってしまうことが考えられます。
故人の自宅に家族が住んでいる場合などは、名義人の変更手続きを早めに行いましょう。
反対に、銀行口座が凍結されていなければ、スポーツクラブや定期購読料などの使っていない会費などが引き落とされ続けます。
不要なものは解約していきましょう。
◆戸籍などの取得
相続手続きには、故人の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人全員の戸籍や住民票などが必要です。
各届出先にこの戸籍等一式を提出しなければいけませんが、返却書類を待ってから次の届出先に提出すると時間がかかったり、
原本が返却されない窓口があったりすると、もう一度同じものを一式揃えなくてはなりません。
最近ではこの手間を省くため、相続関係などの情報を一覧図にし、必要書類を法務局に提出すると
『法定相続情報証明』を必要な枚数発行してくれます。
これは戸籍等一式の代わりとして預貯金の解約、不動産の名義変更などいろいろな場面で利用できるので、複数の手続きが同時に
進められ大変便利でおすすめです。
◆年金受給停止・未支給年金・遺族年金請求
故人が年金受給者であれば、手続きをしないと亡くなったあとにも年金が支払われ、後日返金しなくてはなりません。
一方、故人がまだ受け取っていなかった、亡くなった月ぶんまでの年金があれば『未支給年金』を請求し、受け取ることができます。
そのほか、遺族年金の請求や詳細などは、年金事務所に問い合わせてみましょう。
3ヵ月以内
◆相続放棄・限定承認
相続財産には借金などのマイナスの財産も含まれます。
故人の財産を早めに確定させ、負債が多額であれば、プラスの財産もマイナスの財産も相続しない『相続放棄』が検討できます。
ただし、財産に自宅がある場合は、それも相続できなくなるので相続放棄は慎重に検討しましょう。
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する『限定承認』という方法もあります。
4ヵ月以内
◆準確定申告
確定申告が必要な人が亡くなった場合、その年の1月1日から亡くなった日までの所得が対象になります。
10ヵ月以内
◆相続税の申告・納付
遺言書の有無を確認→相続人の確定→財産目録作成→相続し、相続税の対象であれば申告・納税という流れになります。
戸籍を集めたり、財産の調査、多くの相続手続きなどに追われていると、10ヵ月はあっという間です。
全ては書ききれませんが、その他にも様々な相続手続きがあります。
戸籍を集めて相続人を確定させたり、不動産の相続登記や相続税の申告など、相続人だけで行うのが難しい場合
必要なところは司法書士や税理士などの専門家に依頼するのが安心です。
当センターでは、遺言など生前対策や相続のことについてご相談に対応しておりますので
ご不明なことや気になることがあればお気軽にご相談ください。
(ご相談は無料です)